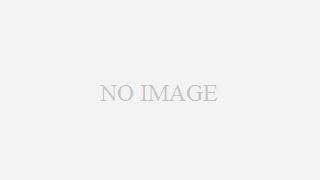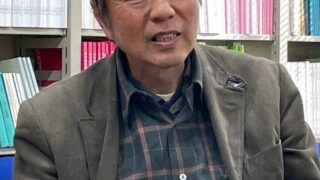今年3月、中国・杭州に約2週間滞在した。昨年9月に初めて北京へ渡航して以来、半年ぶり2回目の中国訪問だ。
とある日の昼食時、一緒に来た日本の学生や先生、現地の学生らと一緒に現地の大学の食堂へ行くことになった。おいしい中華料理を期待しつつ、現地の学生に「学食ってどんな感じ?」と尋ねてみた。すると、予想外にも「まずいです!」という答えが勢いよく返ってきた。
中国の学食は、20種類はあろうかというおかずの中から2、3品と、白米の量を指定して注文する方式が多い。訪れた学食もそうで、私は選んだ3品の炒め料理を恐る恐る口に運んだが、私の当初の期待を裏切ることなくおいしかった。
中国の人は食に厳しいのかと思い、改めてこれが「まずい」のか、よくよく聞いてみた。すると「うーん、普通と思います」との答え。ここで私は、「まずい」と「おいしい」の意見の相違が、言葉の意味合いの違いに起因しているのではないかと思い至った。つまり、日本語の「おいしい」「まずい」と、中国語の「好吃(おいしい)」「不好吃(まずい)」では、指し示す意味の幅に差があるのではないかということである。
日本人同士だって、何が「おいしい」と感じるかは人それぞれだ。同じ言葉を使い、分かり合えているようでいて、すれ違いはきっとあるはず。出身地や出身国が違えばなおさらだ。言葉は万能ではない。だからこそ、多くの言葉を交わして他者を知ろうとする姿勢が大切なのかもしれない。【早稲田大院・浜田澪水】