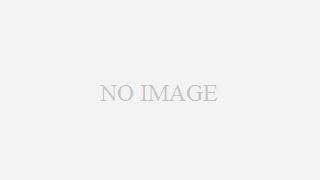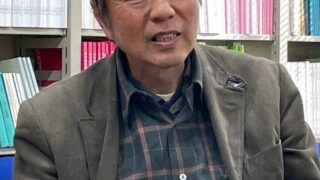1945年8月6日、広島に史上初めて原子爆弾が投下され、同年だけで推計14万人が犠牲になった。現代を生きる私たちは、この悲惨な過去から何を学び、どのように未来へとつなげていくべきなのか。そのヒントを探るため、被爆の実態を今日に伝える写真展「ヒロシマ1945」を取材した。【中央大・朴泰佑】
東京都写真美術館(東京都目黒区)で開催されている本展では、原爆投下直後の広島で市民や記者、写真家らによって撮影された約160点の写真と2点の映像が出展されている。今回の写真展は、これらの貴重な資料を所蔵していた中国新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、中国放送、共同通信社の5社が連携し、初めて共同開催が実現した。
展示の中心は、2023年にこれら報道機関と広島市が国連教育科学文化機関(ユネスコ)「世界の記憶」へ登録を申請した「広島原爆の視覚的資料―1945年の写真と映像」を基に構成された資料群である。
本展の企画と開催に携わった一人が、毎日新聞広島支局の専門記者・宇城昇さん(54)だ。広島出身の宇城さんは、これまで原爆に関する記事を多数執筆してきた。16年には、毎日新聞社内で所蔵資料の検証・精査に取り組むプロジェクトを立ち上げ、その過程で「写真をもっと多くの人の目に触れさせるべきだ」との思いを強めたという。ユネスコへの登録は今年は見送りとなったが、並行して開催準備を進めていた東京での写真展は実現した。
宇城さんは「ジャーナリストにとって写真を撮ることは基本的な行為の一つだが、それすら困難な極限状況の中でシャッターを切った記者たちの思いに目を向けてほしい」と語った。
展示室には、キノコ雲の写真や荒廃した当時の広島の風景、被爆者の姿などが並んでいた。目を背けたくなるほど悲惨な写真の数々。その中で、「伝える」という記者としての使命感のもと、シャッターを切った記者たちの思いが、ひしひしと伝わってきた。
宇城さんはまた、展示写真が当時どのように報道で使われたのか、実際の紙面で紹介したかったと言う。敗戦までの紙面には広島は新型爆弾に打ち勝ったといった見出しが並ぶ。宇城さんは「今で言うフェイクニュースだった」と指摘し、「報道の自由が担保された社会かどうか、改めて考える契機にしてほしい」と話した。
来館者には外国人の姿が目立った。また日本の若者の姿も多かった。米国カリフォルニア在住の男性(45)は、原爆に対する日米両国の認識の違いに衝撃を受けたと話す。「米国が自国に有利な状況を利用して、科学実験のように原爆を投下したうえ、その後の支援も行ってこなかったという事実を、写真を通して実感した」と語った。また東京都杉並区に住む男子高校生(18)は、「人間に対して、なぜこんなことができるのかと衝撃を受けた」と話した。写真展(料金は一般800円、大学生以下無料)は8月17日まで開かれている。