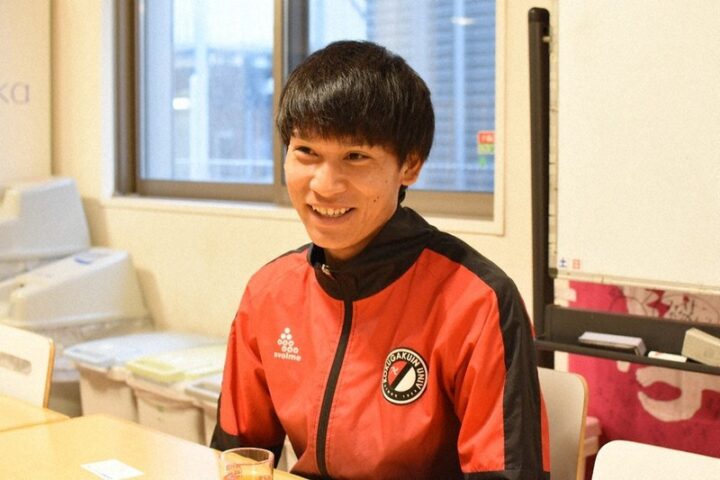父方の大伯母が昨年10月に亡くなった。私が最後に会ったのはその3カ月前。キャンパるの戦争特集の取材で、延々7時間近く話してくれるくらい元気だった。悲しみより、驚きが大きかった。そして、訪ねる度に優しく出迎えてくれた彼女の姿を思い出し、「あの時話を聞けて良かった」という安堵(あんど)感が胸に広がった。
大伯母に聞いたのは戦中戦後の日常生活。「死線をさまようだけが戦争体験ではないはず」という思いからだ。本人は「こんな普通の話で役に立つ?」と、何度も心配していた。しかし私には、「普通のこと」とは到底思えない話ばかり。記事を見せた時の言葉が忘れられない。「こうして見ると、いろいろあったねえ。私しか覚えていないこともあるだろうし、自分でも、何か書いてみようと思ったよ」
何を書こうとしていたのかは分からない。私が記事にした話はきっとその一部でしかない。でも、「食糧不足」とか「公職追放」とか、あの時代を語る単語の裏にどんな生活があったのか。忘れられがちな「灯台の下」を少しは明るくできたのではないだろうか。記事ならではなのは、話し手や書き手が死んでも後世まで残ること。その時代を知りたい誰かの明かりとなる。今当たり前に聞ける話も、書き留めなければ、いつか誰にも分からなくなる、と思い知った。
正月に、鹿児島の大伯母の家を訪ねた。鉢植えが所狭しと庭に並ぶ、いつも通りの風景。今にも出てきてくれそうなのに、鍵のかかった玄関だけが、いつもと違っていた。【慶応大院・瀬戸口優里】