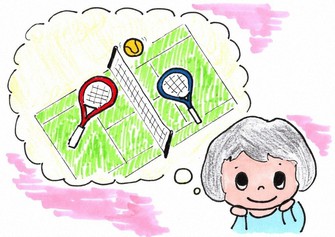2年前に死んだ父の遺影はなかなか変わっている。まず、こっちを向いていない。父の目線はかぶった帽子についたナナフシに向けられている。撮影地はインドネシア。生物学科卒で虫好きだった父は死の3年半ほど前、同じ趣味の友人たちと虫捕りに行った。その時の写真だ。
この遺影らしくない写真を選んだのは私だ。斜め上を見る少しおどけた写真の父とこちらは目が合わない。スーツ姿で真正面を見るような写真を、普通は遺影に選ぶだろう。だがこの写真、遺影らしくはないが、とても「父らしい」のだ。
もとから突拍子もない人で、一緒にいると、とても想像のつかないことをする。自転車に乗れば、「近道」だといって畑の真ん中を突っ切る。歩いていても、急にどこかへいなくなってしまう。学生時代には、野球がしたくて大学の敷地にレンガと土を盛って本格的なブルペンをつくり、怒られて重機で解体された。
そんな父だ。死んだからといって、きっと「らしさ」はそのままだろう。残された私たちのことなんかお構いなしで、好き勝手にやっているだろう。そう思ってこの写真を、遺影に選んだ。堅苦しさとは無縁の表情を浮かべる遺影を見て、葬儀に来てくれた父の知人たちは、「こんな人だった」といって笑った。わざわざ写真を撮って帰る人もいた。
キャンパる取材でも写真を撮る。初めて出会う人やものの「らしさ」を引き出すのは難しい。それでもふと見せる「らしさ」を切り取れればいい。そう思いシャッターを切る。【東洋大・佐藤太一】