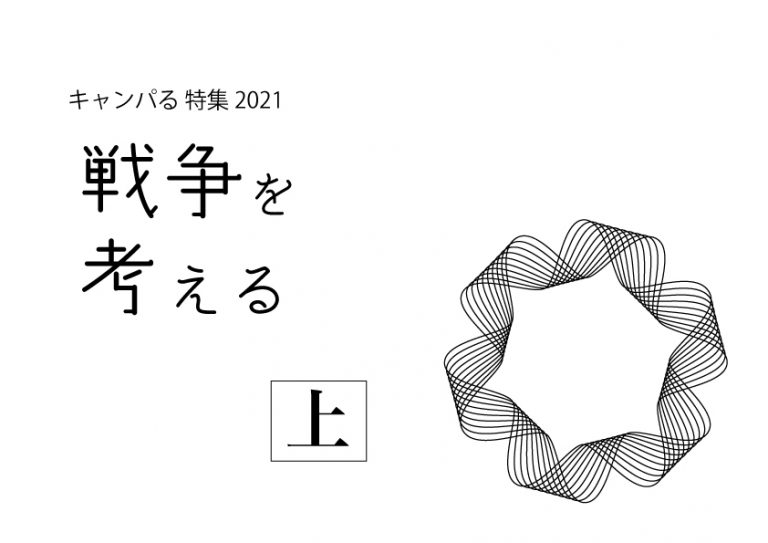<戦争を考える取材班>
太平洋戦争の終結から今年で76年。時代とともに記憶は風化するものだが、新型コロナウイルスの感染拡大や五輪関連のニュースの洪水が、それに拍車をかけている。そんな今だからこそ「平和」を見つめ直し、奪われた日常の尊さを思うべきではないだろうか。今年もキャンパる編集部は3回にわたり、「戦争を考える」企画をお届けする。初回は満州に渡り「性接待」を強いられた佐藤ハルエさん(96)と、「特攻」に翻弄(ほんろう)された多胡恭太郎さん(96)に話を聞いた。
過去のこと忘れない 満州で「性接待」強いられた 佐藤ハルエさん(96)

中国大陸支配のため、日本が1932(昭和7)年に設けた旧満州国。日本は、治安の維持や国境地域の防衛のため、国内の困窮した農民らを「開拓団」として満州に移住させた。岐阜県黒川村(現白川町)も、多数の村民を送り出した村のひとつだ。終戦前後、ソ連の侵攻と治安の悪化で多くの開拓団が追い詰められ、集団自決が続発した中で、未婚女性の性的な犠牲を代償に、団員の多数が生きて帰国を果たせた「黒川開拓団」。そのつらい記憶を語り継ぐ当事者の一人が、佐藤ハルエさんだ。
佐藤さんは、同県佐見村(現白川町)で生まれ育った。生家は養蚕で生計を立てていたが、世界恐慌の影響で生糸の需要が急減。繭の価格が大暴落したことで、生活が苦しくなっていった。その折、父が隣村だった黒川村の開拓団の話を聞きつけたそうだ。そして43(昭和18)年、佐藤さんが18歳の時に両親、父方の祖父母、2歳下の弟とともに家族6人で黒川開拓団に加わり、満州に渡った。
入植した吉林省では、ジャガイモや麦、ソバなどを育てて生活した。開拓団と称していたものの「開拓」とは名ばかりで、実際には現地の住民を強制的に立ち退かせた農地を耕していたという。佐藤さんは農業の手伝いをしながら、満州女子訓練所の「興亜凌霜女塾」(満州女塾)に通った。満州女塾とは、日本から渡った未婚女性に開拓団での生活方法や技術を教える訓練所で、実態は開拓団の独身男性の妻の養成所だった。ただ開拓の理念や人としての生き方など、精神的な教育にも熱心で、「ここでの教えのおかげで帰国できた」と佐藤さんは話す。
満州移住から2年後の夏、日本は敗戦した。「父が張り切って農業一本で暮らすつもりだったから、寂しいのと悲しいのと……」。敗戦後、もともと住んでいた現地の住民が物を盗みに開拓団を襲うようになった。隣にあった熊本からの開拓団は、特に激しい襲撃を受けていたため、ほぼ全団員が毒を飲み、館に火を放って自決した。
それを受け、ピーク時に団員数662人を数えた黒川開拓団でも、団員全員が自決をすべきだという意見が出るようになった。しかし、佐藤さんの父は「そんな簡単な命ではないんだ、日本に帰らなければ」と声を上げたという。
結局、黒川開拓団は集団自決ではなく、帰国の道を模索。現地民の襲撃から開拓団を守ってくれるよう、ソ連兵に警護を頼んだ。そしてその代償に、団は「性接待」役として、未婚の女性を差し出すことになった。「嫁さんには頼めないから、あんたらが犠牲になれ」。総副団長にそう言われ、当時20歳の佐藤さんら15人が、1カ月半ほどソ連兵の相手を務めた。「仕方がなかった。反発はひとつもできなかった。団を守るために犠牲になった」。接待をする中で、4人が性病と発疹チフスで亡くなった。
日本へは46(昭和21)年9月、船で帰国した。自決ではなく帰国を主張した父は、発疹チフスによって祖国の地を踏むことなく亡くなった。足の痛みに悩まされた佐藤さんも数カ月後、ようやく故郷へ戻った。だが、待ち受けていたのは「満州帰りのような娘は汚れているから、誰も嫁にはもらわん」という偏見だった。満州女塾時代の恩師のすすめで故郷から約100キロ離れた蛭ケ野(現岐阜県郡上市)に移住。同地で出会った夫、健一さん(故人)とともに、荒れ地を一から開墾し、農業や酪農で生活をしてきた。「犠牲にされたのはショックだったけれども、その後の生活は幸せ」と佐藤さんは振り返る。
佐藤さんは3男1女を授かり、9人の孫、8人のひ孫に恵まれた。「母は大変な経験をして帰国したが、開拓団が集団自決をしていれば、今の佐藤家はなかった」。取材に同席した長男の茂喜さん(67)は話す。
のまされた苦渋を声高に語ることはしないが、無事に帰れた理由を聞かれれば答える、というのが佐藤さんの姿勢だ。その背景には「黒川開拓団は犠牲があってこそ、みんなを守ることができ、帰ってくることができた」という強い自負がある。取材の途中「昨日のことを忘れても過去のことは忘れない」と佐藤さんが漏らした言葉が忘れられない。【東京学芸大・中尾聖河】
散った若者の真実知って 「特攻」に翻弄された 多胡恭太郎さん(96)

航空機などに爆弾を積み、敵艦に決死の体当たり攻撃をする特別攻撃隊(特攻)。その特攻について二重のやりきれない記憶を持つのが岡山県津山市在住の多胡恭太郎さんだ。特攻隊員になるべく訓練を積み、不慮の出来事で出撃は免れたものの、戦友を特攻に送り出す任務を負わされた。そんな多胡さんは今回、「特攻で散った若者たちの真実を知ってほしい」という強い思いで取材に応じてくれた。
多胡さんは津山市に生まれた。関西学院高等商業学校(現・関西学院大)に在学中の1943(昭和18)年秋、陸軍が航空兵力増強のために募集した「特別操縦見習士官」に志願。採用されて翌年8月、陸軍飛行学校の下館教育隊(茨城県筑西市)に入隊した。当時19歳だった。
多胡さんによると、この教育隊は当時、特攻のためのパイロット養成に取り組んでいた。多胡さんら訓練生はそれを知らされずに入隊し、2カ月後にその事実を初めて伝えられた。もちろん戦って死ぬことを覚悟しての入隊だったが、戸惑いは大きかった。「特攻隊は100%死ぬ。戦闘なら自分の腕が良ければ勝つことができるので、100%死ぬのとは大きく違う」
120人ほどいた訓練生の中には動揺を隠せず、布団の中のほこりをわざと吸い込み、自ら結核にかかろうとした者もいたそうだ。訓練機に乗って行うのは、高高度から突撃目標に見立てた白い目印に向かって降下する、まさに死ぬための訓練。「あの恐怖はきっと伝わらないと思う」と多胡さんは話した。
しかし訓練は、国内の燃料不足のため中断。隊員らは44(昭和19)年末、石油集積地だったシンガポールに移って訓練を続けるべく、輸送船団に便乗して船出した。ところが船団は、経由地の台湾で敵襲に遭い壊滅。訓練を続けられなくなった多胡さんは、現地飛行場の管理に従事した後、45(昭和20)年4月、台湾の宜蘭(ぎらん)に司令部を置く陸軍第9飛行団の作戦室に配属された。
そこで多胡さんに課せられたのは、飛行団傘下の部隊から特攻機を何機、沖縄に飛ばすかを指示する「命令書」作りの任務だった。「特攻として出撃するはずだった自分もこれで助かったと思った」ものの、「自分が書いたたくさんの命令書で、顔見知りの隊員が死んでいく」という罪の意識にさいなまれた。終戦の日まで約4カ月、何度も筆を投げ、夜も眠れない日々を過ごしたという。
戦後、岡山に帰郷した多胡さんは、復学し、高校教員や実家の家業を手伝いながら家庭を持ち、3人の子にも恵まれた。そんな多胡さんは終戦後、戦争体験を長らく語ってこなかった。それは戦争の非情さを知ってもらいたくても、きっと伝わらないだろうという思いがあったからだったという。しかし、つらい記憶を語り継ごうと決意したのは、「今の人は、戦争には行きたくないと言うが、何の努力もなしに平和を保てると思ってはいけない」という思いからだ。
多胡さんは一つの話をしてくれた。45年春、飛行場に特攻機の見送りに行った時のことだ。飛び立つばかりの特攻機が突然、滑走路で旋回し、多胡さんらの元へ向かってきた。多胡さんは幸い助かったものの、隣にいた2人は車輪にひかれ即死だったそうだ。
「特攻隊の隊員はみんな勇んで行ったと思っているかもしれない。しかし実際は最後までみんな迷っていた。いよいよ離陸する時でも何とかして助からないかと思っていた。その心情を分かっていない人が多い」。多胡さんは特攻隊員を、死を恐れぬ名誉の戦士としてとらえるべきではないと悲しそうに言った。「生きたくても生きられなかった。そんな中で若い命が、国を必死に守ろうとしたという事実を知ってほしい」
それが多胡さんの強い思いだ。戦争体験者が少なくなっている今、平和を当たり前だと思わずに、戦争について考え続けることが今を生きる私たちに必要なことなのかもしれない。【日本女子大・安藤紗羽】