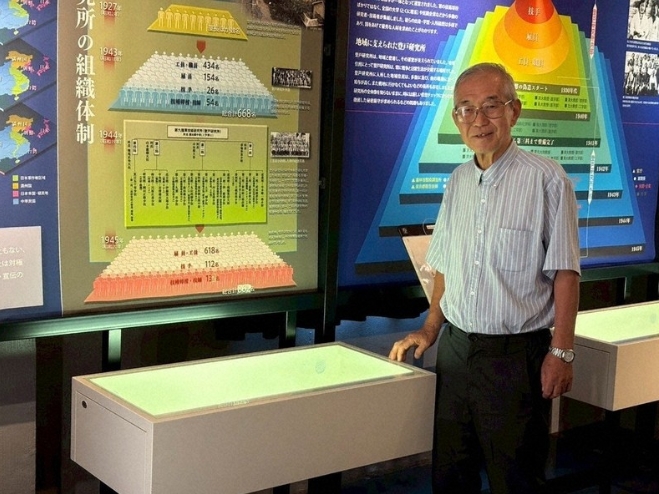戦争の惨禍を再び招かないために、現代を生きる我々には何ができるだろうか。今回は、日本軍が戦時中に仕掛けた秘密戦について学べる「明治大学平和教育登戸研究所資料館」の開設に尽力した同資料館展示専門委員の渡辺賢二さん(82)と、中高生による平和、人権活動を長年見守り続けた広島県福山市の中高一貫校、盈進(えいしん)中学・高校の校長、延和聡(のぶかずとし)さん(61)を取り上げる。【「戦争を考える」取材班】
生物化学兵器や偽札開発「登戸研究所」 加害の事実を見つめて
明治大の資料館開設に尽力 渡辺賢二さん
明治大学生田キャンパス(川崎市多摩区)には戦時中、日中戦争が始まった1937年に陸軍が設けた実験場を前身とする登戸研究所があった。同研究所では風船爆弾や殺人用毒物、偽札など、戦局で優位に立つ秘密戦のための物資開発や研究が極秘裏に行われていた。終戦時に設備や書類は証拠隠滅のために破壊、焼却されてしまい、建物だけが残された状態だった。
研究所には、未成年者も含めて1000人もの人が働いていたとされる。戦時中に秘密厳守を強く求められていた元研究者や職員らは、戦後も長く沈黙を守っていた。
しかし、80年代に転機が訪れた。川崎市が85年から始めた社会教育講座の「平和教育学級」で、歴史の闇に埋もれかけた登戸研究所の存在に光が当たり始めたのだ。当時、法政大学第二高校教諭だった渡辺さんは同講座で登戸研究所について調査を実施。元職員から内部文書の写しの提供を受けるなど、その後の本格的な調査につながる貴重な手がかりを手にした。
同じ頃、高校生の平和学習活動「高校平和ゼミナール」の一環で、同研究所について調べていた長野県駒ケ根市の県立赤穂高校の高校生らも、同研究所の毒物兵器開発責任者だった人物から貴重な証言を引き出していた。駒ケ根市には戦争末期、同研究所が疎開していた経緯があった。
歴史発掘の端緒をつかんだのは、市民や高校生たちだった。渡辺さんは登戸研究所を「洞窟」に例えて語る。「登戸研究所は何もない洞窟みたいなもの。中に資料は存在しておらず、建物だけが残されていた。それを執念で探った」
沈黙を続けることは、元研究者や職員にとっても耐えがたいことだった。元勤務者らは82年に「登研会」という親睦組織を作ったが、同会は明治大に願い出て、89年に研究所跡地に石碑を建立。その後、研究所遺構の保存と活用を求めて活動を開始した。そして署名活動など市民の後押しや渡辺さんらの助力も得て2010年、同大による資料館開設につながった。
渡辺さんは散逸した資料の収集にも尽力した。一つ一つの作業に時間も労力もかかるが、継続できたのは「登戸研究所に勤めた人たちの苦しみを共有したかった」からだという。また国が組織的に手がけた非人道的な取り組みを歴史資料として残すことで「同じような過ちを国が繰り返すことがあることを、若い人たちに伝えたいという思いがあった」と振り返る。
資料館は、同キャンパスの南西の端、現在の西南門近くにある。建物は登戸研究所で生物化学兵器などの研究開発を行っていた第二科の建物を利用。国内では珍しい、戦争遺跡をそのまま利用する戦争資料館だ。第1展示室は全景ジオラマで研究所の活動の全容を知ることができる。第2展示室では電波兵器や風船爆弾、第3展示室は化学技術を応用した殺人用毒物や生物化学兵器、第4展示室では中国の偽札製造の研究内容が展示されている。
渡辺さんは、この資料館を訪れることで「戦争の異常さを感じてほしい」と言う。当時最新の科学技術を駆使して、なぜこんな偽札を作ったり、生物化学兵器を作ったりすることができたのか。「普通は考えられない。倫理的に考えられないことだ。でも国が主人公になって、国が勝てば何でも許されるという世の中になれば、あらゆることが可能になる」
渡辺さんは、今も同大で登戸研究所の講義を担当している。そして同じく資料館開設に尽力した山田朗・同大文学部教授(同資料館館長)とともに、市民や学生向けに資料館などの案内を月に1回は行っている。
夏休みは特に、自由研究のための中高生や親子連れが多く訪れる。7月19日には、東京都立鷺宮高校の高校生2人が、夏休みの「戦争を考える」宿題のため、資料館を訪れていた。引率していた社会科教諭(社会科同好会顧問)の黒田千代さん(45)は「登戸研究所は、日本が戦争で行った加害について考えることができる、数少ない施設だと思っている。加害と被害の事実をしっかりと教えること、知ってもらうことがすごく大事なことだ」と語った。
生徒主体「平和と人権の輪」 広島・盈進中高校長 延和聡さん

ヒューマンライツ部は平和、人権に関する調査研究やボランティアを行うクラブとして、2005年に創部された。部員は中高合わせて25人。(1)核廃絶に向けた取り組み(2)ハンセン病問題の学習(3)東日本大震災などの災害復興支援(4)地元地域でのボランティア活動――の四つを軸に、毎年テーマを決めて活動に取り組んでいる。部の創設を主導し、創部以来20年まで顧問を務め、以降も活動を見守ってきたのが延さんだ。
核廃絶の署名集めが始まったのは08年。きっかけは沖縄尚学高校(那覇市)との交流イベントである「中高生平和サミット」が前年に開始されたことだった。沖縄に招かれ、同校生が基地問題や平和学習を自分の言葉で語っているのを目の当たりにした部員たち。「自分たちも広島の人間として、広島で起きたことを発信する力が必要」と考えるようになり、部員の発案で核廃絶への賛同を募る署名集めを開始した。
同校による署名活動は、生徒会など部外の生徒や沖縄尚学高校、広島女学院中学・高校(広島市)など協力校の生徒も巻き込んで、新型コロナウイルスの感染拡大期間を除いて毎年行われている。夏になると福山市や広島市で複数回、生徒たちが署名を求めて声を上げる。
これまでに集めて国連本部に送った署名は約70万筆。実績が認められ、14年からは「ユース非核特使」として、外務省が盈進の生徒をニューヨークやウィーンで開かれる国連のNPT(核拡散防止条約)会議に派遣するようになった。
毎年引率として署名集めを見守ってきた延さんには忘れられない光景がある。署名集めを始めた年、想像以上に素通りしていく人が多い。生徒たちが必死に声を張り上げても、「そんなもの集めても意味がない」「学生は帰って勉強しろ」と心無い言葉をかけられることもしばしば。「最初は泣いていた子もいた」と生徒たちの姿を振り返る。
しかしそんな中で、署名を書いている最中にぼろぼろと泣き出す一人の高齢女性がいた。聞くと彼女は、自分が被爆孤児であることを長年周囲に言えていなかったという。生徒らが署名を呼びかける姿を見て「暑い中頑張ってくれている」と感動して名前を書きに来てくれたのだ。「このおばあさんの思いに応えたいという気持ちが、生徒たちを動かす。教員の言葉では続かない。こういう感動を自分で発見するから、活動が続いていく」
人権問題を重視する延さんの原点には、成長期の体験がある。幼少期、教員である父親の赴任先で同和地区の人々と親しく交流した。小学校時代には、水俣病問題やベトナム戦争について、強い問題意識を持つ教員と出会った。「その先生が熱く語ってくれたから、私に核廃絶やハンセン病問題の精神が根付いた」と話す。ただ、ヒューマンライツ部が創部以来20年間、活動を続けてこられた理由に、延さんが自分自身を挙げることは決してない。
「教員が生徒にああだこうだ言っても、届くのは10分の1くらいしかない。でも、先輩や友達の話はちゃんと全部入ってくる」。だからこそ、顧問として指導することよりも、学びの場を整え、それを生徒同士で受け継いでいくコミュニケーションの機会を作ることに腐心してきた。
署名集めをしていたある夏、街頭で生徒たちが「君たちは教員にやらされているんだ」と絡まれたことがあった。その時、生徒の一人がメガホンをとって「私たちは自分の意志でやっているんです!」と叫び返したという。「そういう姿を見ると、私もうれしい。子どもたちにそんな力があったのかと思い知らされた」と語る延さん。生徒たちの将来に期待を込めて「もっと仲間との絆を深めて、もっと独創的に、もっと自由に、もっと地域に根ざして、もっとグローバルに平和と人権の輪を広げてほしい」と語った。